特別企画
ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう

ギャラリーやイベントでA列車をとことん楽しみましょう
A列車で行こう ポータルサイト > 特別企画 > A列車jp発「お出かけ、えちごトキめき鉄道」


目次
えちごトキめき鉄道はその名の通り、越後国――新潟県に2路線を持つ、第三セクター鉄道。愛称は「トキ鉄」です。
その2路線のうち「日本海ひすいライン」は、富山県がすぐ近くの市振駅と、新潟県上越市内にある直江津駅のあいだ59.3kmを、日本海へ沿うように結びます。
「ひすい」は、沿線が翡翠の産地(新潟県糸魚川市周辺)であることが由来です。
もうひとつの路線「妙高はねうまライン」は、直江津駅から南に延びる37.7kmの路線。長野県のすぐ手前にある妙高高原駅まで走ります。
「はねうま」は、沿線にそびえる妙高山の山肌に、春、雪解けによって現れる跳ね馬のような形が由来です。

元々この2路線は、別の「本線」でした。
えちごトキめき鉄道の日本海ひすいラインは、米原駅(滋賀県米原市)から新潟県の直江津駅に至る国鉄・JR北陸本線の一部でした。
北陸新幹線の開業によって、それと平行する区間の北陸本線がJRから経営分離され、生まれたのが、えちごトキめき鉄道の日本海ひすいラインになります。
北陸本線は、日本海沿いに関西~東北・北海道間を結ぶ運行系統「日本海縦貫線」の構成路線で、物流の大動脈でした。
この役割は、えちごトキめき鉄道の路線になってからも同じ。日本海ひすいラインには引き続き、多くの貨物列車が行き交っています。
えちごトキめき鉄道の妙高はねうまラインも、北陸新幹線の開業によるJRからの経営分離で生まれました。
こちらは元々、高崎駅(群馬県高崎市)と新潟駅(新潟市中央区)を結ぶJR信越本線の一部で、関東と北陸を結ぶルートを構成。
JR時代は、現在の妙高はねうまラインと日本海ひすいラインを直通し、上野~長野~直江津~金沢間を結ぶ特急「白山」や急行「能登」も運行されていました。
異なる「本線」だった、えちごトキめき鉄道の2路線。その性格も、いろいろと異なっています。
日本海ひすいラインは「海」の路線。沿線の各所で、ちょくちょく日本海の車窓を楽しむことが可能です。

妙高はねうまラインは「山」の路線。港町にある直江津駅と、妙高山(標高2454m)の麓にある妙高高原駅のあいだには約500mの標高差が存在し、途中で、鉄道が山を越えていく工夫のひとつ「スイッチバック」も通ります。

また日本海ひすいラインの列車は、基本的にET122系ディーゼルカーを使います。
線路は電化されている(線路の上に電気が流れる架線がある)ものの、梶屋敷~えちご押上ひすい海岸間において、電気の種類が直流と交流とで変わることから、電車を使いたい場合、交直両用の電車が必要です。
しかし、交直両用の電車はいろいろと高コストになるため、安く済むディーゼルカーを使っています(JR貨物が日本海ひすいラインで運行する貨物列車は、交直両用の電気機関車を使用)。
妙高はねうまラインの列車は、基本的にET127系電車を使います。
直流専用の電車なので、途中で電気が交流に変わる日本海ひすいラインでの運行には向きません。
これら2路線の直通運転は、そうした電気、車両の違い、需要などの事情から、ごく一部の普通列車と、後述する観光列車だけで実施されています。
「A列車で行こう9」「A列車で行こうExp.+」には、日本海ひすいラインでおもに使われるET122系ディーゼルカーを収録。

日本海の波をデザインした車両なので、海沿いを走らせれば似合うでしょうし、あえて山の中で走らせるのも、想像がふくらんで楽しいかもしれませんね。
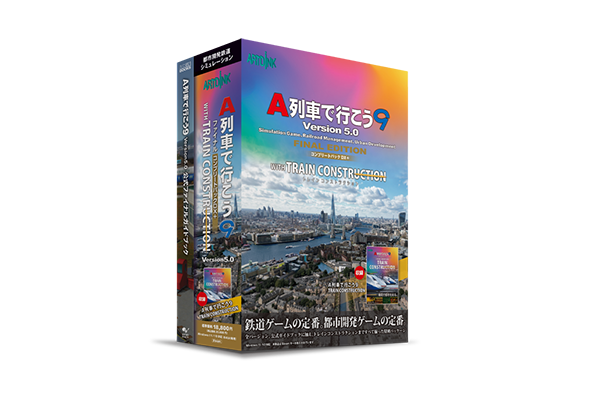
A列車で行こう9 Version5.0 コンプリートパックDX+
Windows (Steam)
えちごトキめき鉄道の日本海ひすいラインでは、筒石駅(新潟県糸魚川市)が「名物駅」になっています。
トンネルの途中にある珍しい駅で、地上の駅舎からホームまで、約290段の階段を降りていかねばなりません。

筒石駅があるのは、在来線で有数の長さ(1万1353m)を誇る頸城(くびき)トンネルの途中です。地下鉄の駅みたいでもありますが、到着したそのホームは、都会のように明るくはなく、賑やかでもなく、静かな非日常の空間。異世界気分が楽しめるかもしれません。
ちなみに、トンネルの奥深くにある筒石駅ホームは涼しいため、夏の訪問地としてオススメ。貨物列車などの通過時は強い風が吹く場合があるため、そのときはホームから出るなど、くれぐれも注意してください。

筒石駅から1kmほど歩くと、日本海に面した筒石の漁港、集落に出ることもできます。ズワイガニ、タイなどが水揚げされるそうです。
えちごトキめき鉄道の妙高はねうまラインにも、「名物駅」があります。スイッチバック構造の二本木駅(新潟県上越市)です。
「スイッチバック」とは、進行方向を変えながらジグザグに進むことで、急な坂道に対抗する方法。
二本木駅の場合は、急坂の途中に駅を設置するため、スイッチバックが採用されました(急坂の途中から平坦な場所へ線路を引き込み、そこへホームを設置。駅に停車しない列車はスイッチバックせず通過できる)。

直江津駅側から急坂を登ってきた列車は、二本木駅へ到着する直前に引き込み線へ入り、いったん停車。そこで進行方向を変え、バック運転で二本木駅ホームに到着します。
二本木駅ホームからは当初の向きで出発し、そのまま妙高高原駅方面へ進行。山を下りて直江津駅側へ行くときは、逆の流れです。
こうしたスイッチバックは全国的に珍しく、新潟県内では二本木駅だけにあります。
ちなみにバック運転時、運転士は席を移動しません。乗務員室の窓から顔を出し、後ろを見ながら列車を走らせます。
さて二本木駅は、「レトロ」もポイント。
1910年(明治43年)に建築された当時の駅舎、レンガ造りの小屋などが残っており、珍しいスイッチバック構造とあわせて、途中下車しての散策をオススメしたい駅です。

豪雪地帯にあるため雪対策の設備も多く、スイッチバックの引き込み線には、1922年(大正11年)に設けられた木製の雪覆い(線路を雪から守る設備)が現役で使われています。
個性的な車窓、駅がそれぞれの路線にある、えちごトキめき鉄道。一度にその両方を満喫できてしまう列車もあります。観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」です。
日本海ひすいライン、妙高はねうまラインにまたがって運行され、国内最大級という天井まで回り込んだ窓から日本海、妙高山といった絶景を、旬にこだわった新潟の食材に舌鼓を打ちながら楽しめます。

筒石駅、二本木駅では駅を見学できるほか、北陸新幹線が停車する上越妙高駅、糸魚川駅発着で運行されるため、乗車しやすいのもポイントです。
この「えちごトキめきリゾート雪月花」は、電気の種類に影響されないディーゼルカーなので、日本海ひすいライン、妙高はねうまラインにまたがっての運行が可能。「A列車で行こう9」「A列車で行こうExp.+」にも収録されています。

路線を選ばず、優れた眺望を楽しめるという特徴を生かして、海あり山ありの幅広いエリアで活躍させてみたいですね。
えちごトキめき鉄道にはもうひとつ、路線をまたがって運行する観光列車があります。その名も「国鉄形観光急行」です。
これは関西と北陸を結ぶ急行列車や、北陸エリアの普通列車などで使われてきた国鉄455系電車、国鉄413系電車を使った列車で、交直両用車両のため、幅広く走ることができます。

「国鉄形観光急行」は文字通り、国鉄時代の雰囲気を今に伝えている貴重な列車です。車内に入った瞬間、視覚的に、聴覚的に、そして嗅覚的に懐かしくなる人が、きっと多いことでしょう。
架線の電気が直流と交流で切り替わる場所(梶屋敷~えちご押上ひすい海岸)では、それに関連し、車内の照明がしばらく暗くなります。
かつては日本中にある同様の切り替え区間(デッドセクション)で日常的に見られた光景ですが、現在ではレアな体験になっています。
こうした切り替え区間を通過する際、現代の車両は搭載したバッテリーの電力を使うため、照明が消えないからです。
この意味でも「昔の列車」を楽しめる「国鉄形観光急行」。古い車両なので、国鉄時代を知っている人にはもちろんですが、知らない人にこそぜひ一度、元気で活躍しているうちに乗って……いえ、体験してみてほしいと思います。
掲載日:2025年7月25日
提供:A列車で行こうポータルサイト「A列車jp」(https://www.atrain.jp/)
